

|
2004/3/28
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
グラフからは、残念ながら「期末買い」による株価上昇を期待することはできません。それどころか、平均ではマイナスになっています。特に第1四半期末である3月末については、過去5年間、前日比はずっとマイナスです。
2003年9月期末
2003年6月期末
2003年3月期末
グラフからは、6月期末日、12月期末日に、大きな出来高を伴っている一方で、3月期末、9月期末は普段と変わりがありません。 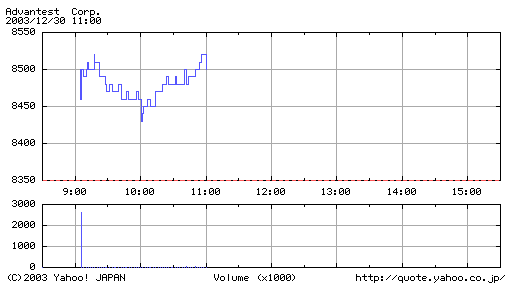 |
2004/4/4
日米の2大スーパースターの予言が示すもの
最初の予言は、アメリカ代表の「金持ち父さん」のものです。ロバート・キヨサキ著の作品に「金持ち父さん」として登場する方です。この考えは「金持ち父さんの予言」ロバート・キヨサキ著の本の中で記載されています。
次の予言は、日本代表の「斉藤一人」さんのものです。「銀座まるかん」の創始者であり、1993年以来、全国高額納税者の10位以内を続けている、文句なし所得No.1 の方です。この考えは「斉藤一人の世の中はこう変わる」小俣貫太著の本で記載されています。
私が日米の2大スーパースターだと思う人物が、これからの時期の株高を予測しているのがとても興味を引きました。2人とも、世界の潮流および法律の影響から、時代の先を読むことが非常に上手い方々です。
今回の投資戦略は、嗜好を変えて、この予想に、静かに耳を傾けてみることにします。
最初に、この予言の元となる、日米の年齢別人口構成を見てみましょう。鍵となるのは、日米とも、丸で囲んだ第二次世界大戦後の「ベビーブーマー」と呼ばれる56歳以下の層の存在です。
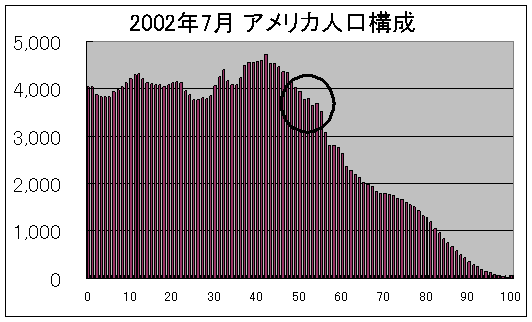
※上記データは米国sensusより引用
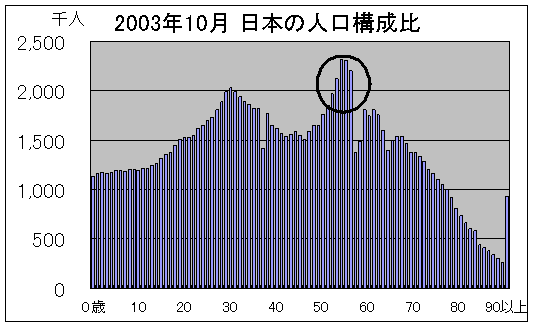
※ 上記データは総務省統計局から引用
まずは、「金持ち父さん」から。
「法律の変化が未来を変える」「今回の法律の変化は史上最大の好景気と不景気をもたらすであろう」と述べています。この法律とは「エリサ法」、いわゆる「401k」に関するものです。
「401k」とは、ざっくり言って、今まで企業や国が決めていた老後の年金支給額を、自分の投資技術で年金支給額が決まるようにするための法律です。日本でも「確定拠出金制度」として、法律が制定されました。
金持ち父さんは、この法律による株式暴落の予想を中心に置いています。
暴落の理由として、この法律には 70.5歳を超えたら、毎年必ず8%相当額の資金(その多くは株式)を引きおろさなければならない条文が入っているからです。そしてこの 70.5歳に、戦後のベビーブーマーが到着する(2016年)頃に、悲劇が起こると予想しています。
この悲劇に関する詳しい話は、本に譲るとして、この悲劇の前に、ベビーブーマーたちが引退前の最後のチャンスとて株式市場に殺到すると予想しています。
次に「斉藤一人」さんから。
「今回は、売り逃げする必要がないほど、どんどん上がっていく」と述べています。その理由は明確に示していませんが、金持ち父さん同様、引退を直前にしているベビーブーマーの存在に目をつけているのではないかと思っています。
現在でも「4千万以上の資産」を持ち、これから得る「退職金」、そして十分な「年金」の権利を獲得したこの世代が60歳で定年引退すれば、仕事で使う暇もなかったお金を、夫婦の旅行や孫の面倒のために、消費に回すのは明らかです。
ここで注意しなければならないのは、斉藤一人さんは「物価はまだまだ下がり続ける」「失業率は改善しない」「本格的な景気回復はない」と一見矛盾したことも予言しています。こられは、法的な問題と人的な問題があると指摘しています。
この問題と株価上昇との関連は本に譲るとして、株価が上昇することは間違いがないと見ているようです。
結論:
・2大スーパースターは人口構成、法律等による観点から、株価が上昇すると予想している。乗り遅れることなく、基本は買いスタンスで望むべし。
・金持ち父さんは同時に、暴落も予想している。少なくとも2016年までには、暴落が起きても大丈夫な技術(信用売り、プットオプション)を磨いておくべし。
私も今後、基本は買いスタンスに置き、暴落に備えてオプション取引に参加しようと考えています。
最後にもう一度、この予言が記載されている本を紹介します。どちらも長期的な展望から今後を予想した、示唆に富む書物です。世界観が変わることでしょう。
・「金持ち父さんの予言」 ロバート・キヨサキ著
・「斉藤一人の世の中はこう変わる」小俣貫太著
![]()
2004/5/16
金利上昇で株価は下がる?
その理由として、「金利が上昇すれば、国債などの債券の利率が上昇する」。そうすると、「比較的安全な債券でも、十分な利益が得られる」。その結果、「株の資金が債券へ流れ、株価が下落する」というものです。
確かに論理的には合っていそうです。しかし本当の所はどうなのでしょうか。早速過去のデータを見て、この論理の正当性を確かめてみましょう。
最初に日本のデータから見てみます。過去20年ほど調べてみると、金利上昇局面は1度しかありません。かの有名なバブルを抑えるための金利上昇('89-'91年)です(図中の青線が金利の推移(右目盛)、黒線は日経平均値(左目盛)を表しています)。
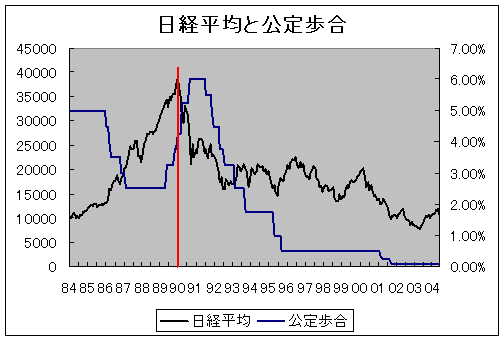
確かにこれを見る限り、金利が上昇した影響を受け、株価が下がって(暴落して)います。ただし、金利が上昇しても、しばらくは株価は上昇します。赤い線の株価最高値の時期は、金利上昇途中です。
次に米国のデータを見てみます。過去20年ほど調べてみると、金利上昇局面は3度ありました。'87〜'89年、'94〜'95年、'99〜'2000年です。
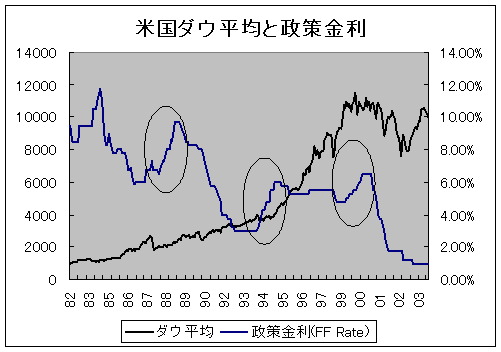
どの金利上昇局面でも、株価が下落しているようには見えませんが、よくわかりません。もうちょっと分かりやすくするために、この3度の上昇局面(1次〜3次)を拡大して、グラフにしてみます。
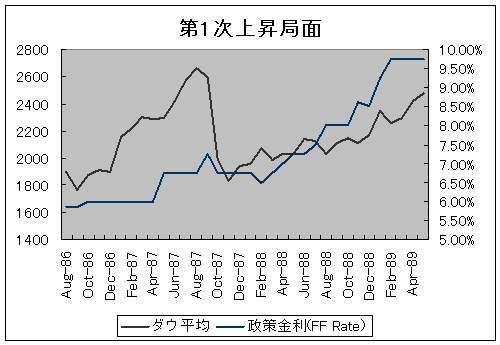
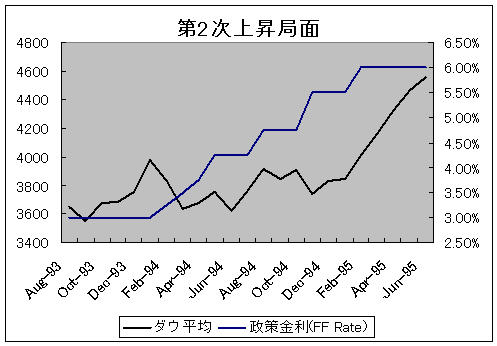
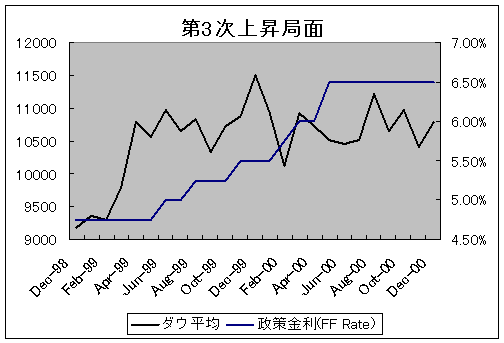
いずれの局面でも株価は下落していません。第1次、第2次の上昇局面では、利上げの最終段階では、株価が上昇しています。第3次は、株価がボックス相場を形成しています。
結論1:
・金利が上昇すれば株価が下がると言われるが、近年の米国の相場では当てはまらない。従って、この理由だけで株を売却するのは合理的な行動とは言えない。
さらにもう一つ、米国金利が上がると、日本の株価が下がる理由がささやかれています。それは、米国の金利が上昇すると、日本との金利差が開き、米国内の金利で利益が得られます。その結果、日本に投資する旨みが消え、日本から資金を引き上げるというものです。
確かに一理あります。この件についても調べてみましょう。過去20年程の日米の金利差と、日経平均の株価の推移です。「金利差=アメリカの金利-日本の金利」として表しています。
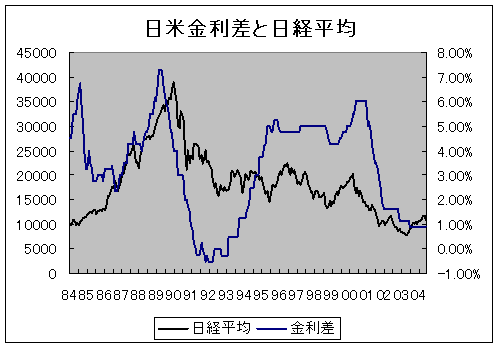
グラフを見る限り、真実は逆で、金利差が開く(米国の金利が高くなる)と、日経平均が上昇しています。しかもその相関がはっきり見て取れます。
結論2:
・過去20年を見る限り、米国との金利差が生じれば、株価が上昇する傾向にある。従って、「金利差が開くから」との理由だけで、日本の株を売却するのは合理的な行動とは言えない。
つまり、「米国の金利が上がると、日本の株価が下がる」というのは、過去の例からは真実ではありません。
なぜ金利が上昇しても、株価が下がらないのでしょうか?
確かに「他の全ての条件が不変かつ一定ならば」株価は下がることになります。つまり、円ドルレートも、経済成長率も、世界情勢も、石油の価格も、人々の生活嗜好も変わらなければ、金利が上昇すると、株価が下がります。でも実際の世の中はそんな単純ではありません。
米国の金利が上昇するということは、米国の経済の調子が良いことを意味しています。そうすれば、日本から輸出が増え、日本国内景気も活性化されることでしょう。
米国の金利が上昇するのは、日本の投資家にとって、買いのチャンスとなる可能性が大と言えます。
![]()
2004/5/30
新規株式公開が多いと株価が下がる?
でもちょっと気になったのは、新規株式公開のためのブックビルディングが活発化するタイミングとも一致したことです。
もしかしたら、新規株式公開の波と、株価の上下の波との間に、何か関係があるのではないでしょうか。もし関係があるとすれば、大発見なのですが、どうなのでしょうか...
早速グラフで、昨年の9月からの新規公開企業数(IPO数)と株価の関係をグラフにして見てみます。(グラフ中、左目盛は、9/1日を100%として、そこからの株価上昇率を記載しています。右目盛は1日あたりの新規公開企業数です)
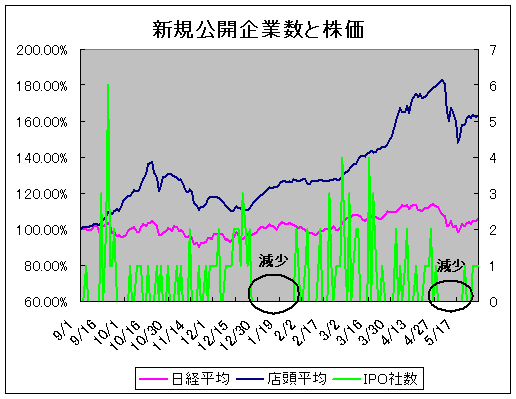
グラフから、過去に極端に新規公開企業の数が減少したのは、年明けの1月上旬とゴールデンウィーク明けの5月上旬であることがわかります。
しかしながら、1月上旬は株価が上昇し、5月上旬は下落しています。このグラフからは、IPO数の減少と株価については、はっきりとした関連は見当たりません。
もう少しグラフを良く見ると、逆にIPO企業数が増えた後で、株価が上昇しているように思えます。そこで別の切り口として、新規公開企業の公募金額(ブックビルディングで実際の販売額)と、株価との関係を見てみましょう。
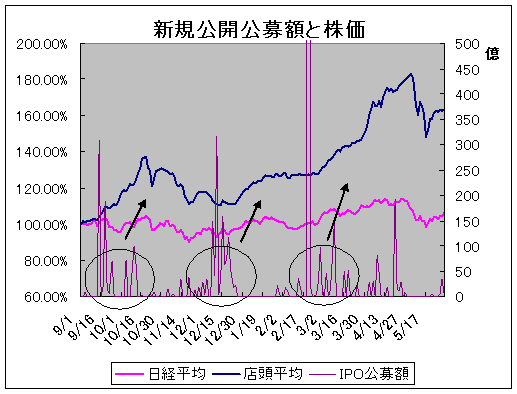
面白いことが分かってきました。新規公開株の公募額が大きい(1,000億規模)と、その後の株価に「上昇」の影響を及ぼしています。因みに、グラフ中、額が上に突き抜けているのは、2/19日、新生銀行の2,300億の新規公開株公募です。
ところで、なぜこんなことが起こるのでしょうか?
最近では、新規公開株の公募額と、実際の初値には、2倍ほどの開きがあることは当たり前になってきました。つまり、公募し当選すれば、公募額と同等の利益は約束されたも同然です。
この結果、利益分の余裕ができた投資家が、さらに株式購入資金とし、利益を株価購入にあてます。その結果、株価が上昇します。
つまり、公募額と初値との価格差が株式上昇の燃料になっているのではないでしょうか。
結論:
・新規公開株の減少期と株価には関係がない。
・新規公開株の公募額が増加するほど、公開後に全体の株価上昇が待っている。戦略としては、大型の新規公開株が市場に販売されたあたりで、資金を市場に投入すべし。
これからの新規公開株の公募額が増加する時期は、まだ見えていませんが、東証が上場するあたり(いつでしょうかね)に怒涛の上昇チャンスがやってくるかもしれません。
ただし、まだ新規公募金額が、初値との間に2倍ほどの差が出ていることが条件ですが。
![]()
2004/8/1
8月は「夏枯れ相場」「サマーラリー」どっちが本当?
どちらも夏の相場の格言なのですが、一体どっちが本当の姿を言い表しているのでしょうか。過去を調査することで、はっきりさせることにしましょう。
まずは、ここ12年間の8月の日経平均の推移を見てみましょう。8月最初の日の終値を100%として、そこからどのように株価が推移したかをグラフにしてみます。
横軸は、8月の営業日数を表しています。1-5 が8月第一週、6-10が8月第二週です。また太字の線は、オリンピックのあった年です。
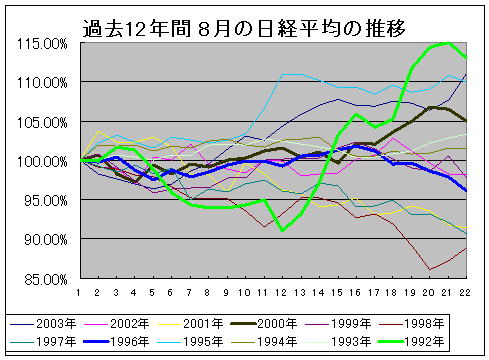
結構バラバラな動きですね。ただ、なんとなくわかるのは8月前半の動き(7-10営業日の8月第二週近辺まで)がおとなしく、8月後半に突然として動き出しています。
因みに、1992年の株価(緑色の太線)の後半急上昇は、「日銀の金融緩和策」「大型公共投資を軸にした景気対策」「PKO呼ばれる政府による事実上の株価維持政策」によるもので、「相場に人為的な手が入った」ことを感じさせます。
ここで、もうちょっと分かり易くするため、12年間の平均値を取り、株価の推移をグラフ化してみます。
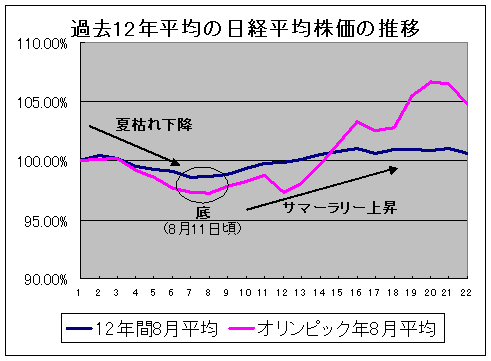
傾向がはっきりとしてきました。オリンピックの年も全体としても、8月の8営業日あたりまで、ゆるやかな下降で底を打った後で、ゆるやかに上昇しています。
この8月の8営業日は、今年(2004年)で言えば、8月11日(水)です。まさに、お盆休みの開始日に相当します。機関投資家や個人投資家が銘柄を整理し、ゆっくり休みに入る姿が目に浮かびますね。
結論:
・「夏枯れ相場」は存在する。8月のお盆休みに入るまで、全体で動きが乏しく、ゆるやかに株価が下降する傾向がある。
・「サマーラリー」も存在する。お盆休み中から徐々に株価が上昇する傾向がある。
結局は「夏枯れ相場」も存在し、「サマーラリー」も存在し、どちらも夏相場を言い表していることになります。どうせなら、「お盆底」とでも名付けたら正確に言い表しているのですが。
もし、これを戦略として利益に結びつけるとすれば、お盆前までは「売り」姿勢、お盆に入ったら「買い」姿勢で対応するのが良さそうです。
(2004/8/4追記)
今年は曜日配列の関係上、8月9日から夏休みに入る企業が多いようです。そこで、過去、今年と同じ曜日配列となる、8月1日が日曜日パターンの 1993年と 1999年のグラフをクローズアップしてみます。
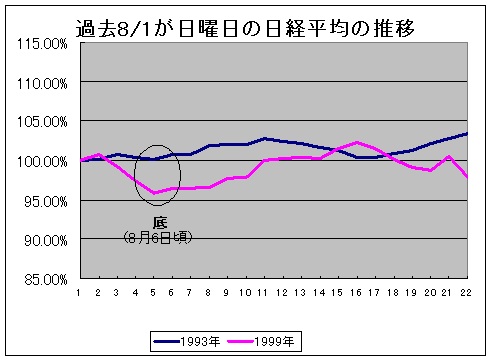
見事に底が「夏休み前」の5営業日目(8月6日)にきています。ということは、過去のわずかな例からですが、今年は、8月6日の金曜日を底にして、株価が反転する可能性が高いと考えられます。ということで、今年は、買いスタンスを多少前倒ししても良さそうです。